「片づけよう!」と思ったとき、まず収納用品を買いに行っていませんか?
実はそれ、最後のステップです。この記事では、整理収納アドバイザーの学びをもとにした8つのステップと、実家の父の部屋を整えたリアルな実例からの気づきをまとめます。
ムダ買いを防いで、ラクに続く仕組みを一緒に作りましょう。
整理収納の8つのステップ
片づけは順番が9割。飛ばさず進めると、収納は自然に決まります。
所有の意味を考える
- それは今の自分(家族)に必要か、役割は何か。
- “いつか使う”ではなく、“いつ使うか”で判断。
モノの本質を知る
- 大きさ・重さ・扱いやすさ・使用場所・使用者(大人/子ども)。
- 本来の使い方/頻度を言語化すると迷いが減る。
整理のねらいを明確にする
- 例)朝支度を時短/掃除をラクに/安全性UP(地震対策)
- 目的が具体的だと判断基準がブレない。
ねらいからグループ分けする
- 用途別・使う人別・場所別に仲間分け。
- 例)「お出かけセット」「書類(学校/医療/保険)」
使用頻度でさらにグループ化する
- 毎日/週1~月1/年数回でゾーニング。
- **一軍(毎日)**は一番取り出しやすい位置へ。
収納を分析する
- 収納のサイズ・奥行き・可動棚・動線を計測。
- 「四角く区切る」前提で箱の入り数をイメージ。
グループと収納を重ねる
- グループ(量)に合う場所・容器を選定。
- ここで初めて収納用品を検討するのが正解。
指定席の完成(定位置管理)
- ラベルを貼り、家族に共有。
- 収納は**8割収納(2割の余白)**で回転を良くする。
- 成長や季節で定位置を更新するのが維持のコツ。
実例:実家の父の部屋を整えたら見えたこと
ものに溢れ、埃まみれ。棚は天井近くまでぎっしり——地震を想像するとゾッ。
クローゼット:まずは“全出し”
- 体型変化で着られない服、好みでなく全く着ていない服、毛玉だらけ、過剰な下着・靴下…を仕分け。
- 9個あった引き出しを5個に削減。
- シャツなどシワになりやすい服はハンガーへ。掛ける量が適正化して取り出しやすさが向上。
本・書類の棚:所有の意味から見直す
- 仕分けは父が主体で実施。読み返す基準・保管期限を設定。
- ここで判明:収納用の箱が大量に! →「片づけようと思って、とりあえず収納用品を買った」とのこと。
この実例からの教訓
- 収納用品は最後に買う。
- “置く場所・しまうもの・必要量”が決まってからでOK。
- 見た目重視でサイズ不一致を買うと、お金もスペースもロス。
収納の目的を言葉にする(ブレないための軸)
- 「朝の支度を5分短縮」「掃除を10分短縮」など時間で定義。
- 「地震で落ちない配置」「重い物は下段」など安全で定義。
- 家族が“自分で戻せる”仕組み=家事の分担が自然に進む。
使いやすく・続けやすい収納のコツ
- 四角く区切る(仕切り・ケースで空間を面で捉える)
- **8割収納(2割のゆとり)**=出し入れがスムーズ
- ラベルで「見れば分かる」状態に
- 動作数を減らす(開けてすぐ取れる/戻せる)
- 定期的に定位置を更新(子の成長・季節・趣味の変化)
よくある失敗 → こう直す
- 失敗:SNSの美収納を真似してサイズが合わない
- 対策:採寸→設計→購入の順番を守る
- 失敗:“とりあえずボックス”が増殖
- 対策:グルーピング→量の把握→適正サイズの容器
- 失敗:満杯収納で戻すのが面倒
- 対策:2割の余白+動線最短の配置
今日からできる15分タスク(ミニ課題)
- よく使う引き出しを1か所だけ全出し
- 「要る/要らない/保留」に仕分け(保留は箱1つまで)
- 使用頻度で並べ替え、上段=一軍に
- 仮ラベル(マスキングテープでOK)を貼る
- 1週間使ってみて、ラベルを清書
まとめ
片づけの順番は、整理 → 収納。
収納は“使いやすく戻しやすい”を設計する作業。
収納用品は最後に買うと、失敗もムダも激減します。
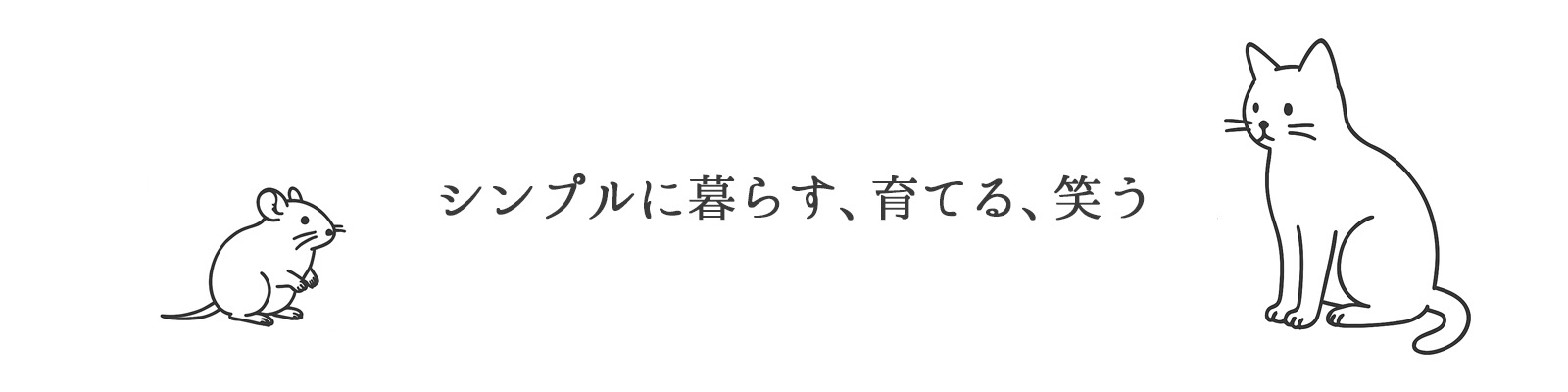
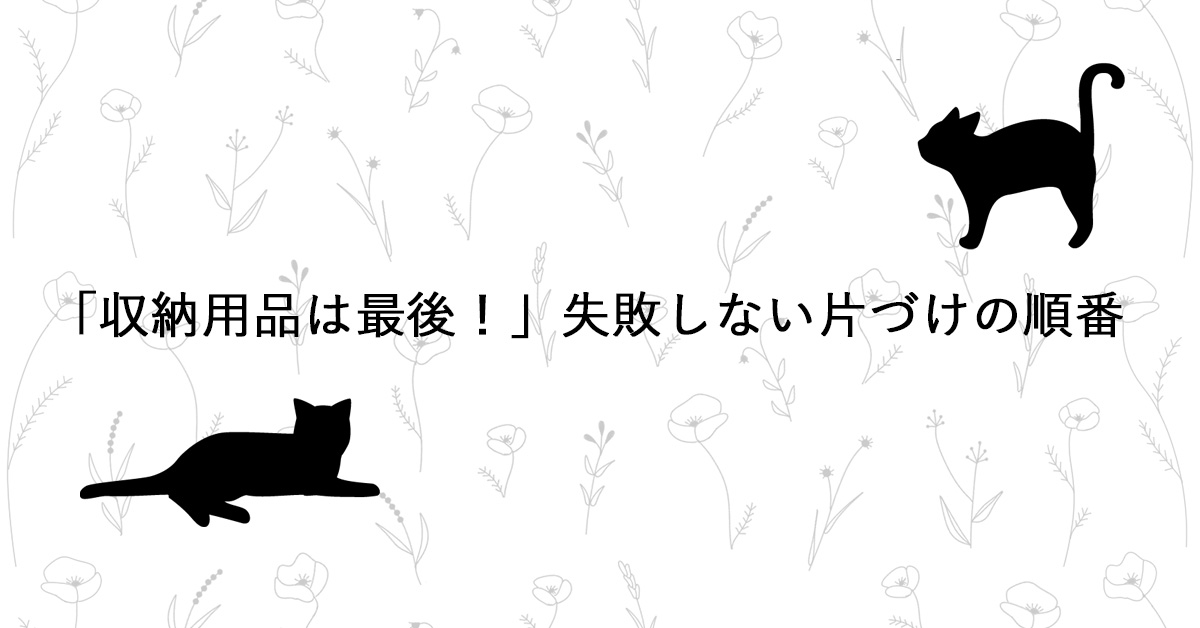


コメント